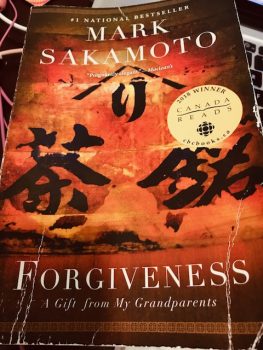
今年読んで良かった本の2冊目は、マーク・サカモト氏によるForgivenessという本です。
この本は2018年のCanada Readsというおすすめ本コンペティションの優勝作品となり、前年に出版された本にも関わらずベストセラーになりました。日系カナダ人の書いた本ということで日系コミュニティでも話題になり、多くの人が手に取ったようです。私も含め。
Read more
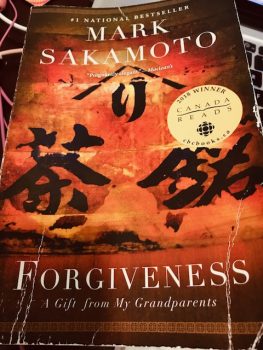
今年読んで良かった本の2冊目は、マーク・サカモト氏によるForgivenessという本です。
この本は2018年のCanada Readsというおすすめ本コンペティションの優勝作品となり、前年に出版された本にも関わらずベストセラーになりました。日系カナダ人の書いた本ということで日系コミュニティでも話題になり、多くの人が手に取ったようです。私も含め。
Read more
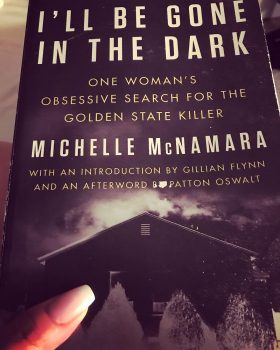
2018年は、書くことも少なかったですが読んだ本も少なかった。。。ですが、数は少なかったものの数冊の良い本にも巡り会うことができました。今日はそのうちの一冊を紹介したいと思います。
I’ll Be Gone in The Dark by Michelle McNamara
北米ではいまTrue Crime(犯罪もの)というジャンルが本、ドキュメンタリー映画、ポッドキャストなどでものすごく流行っているのですが、私も去年あたりからMy Favorite Murderというポッドキャストにハマり、今年はライブショウにも行ったほどの大ファンです。ですが、True Crimeの最初の媒体ともいえる本に関してはほとんど読んでおらず、この本の著者のミシェル・マクナマラも全く知らなかったのですが、ポッドキャストで話題になっていたため、手にとることになりました。
Read more

ブレネー・ブラウンの最新刊、彼女の4冊目の本、Braving the Wildernessが今月発売され、さっそく購入して読みました。今回の本はそこまで厚くないので、結構さらっと読めます。
Braving the Wildernessとは、どういう意味でしょうか。Wildernessとは荒野や野生という意味ですが、Braveを動詞として使ってあるので「荒野に立ち向かう」などと言った意味になります。
一体どういう内容なのか、ほとんど予習をせずに購入し読み始めたのですが、とりあえずこれまでのおさらいをすると、ブレネーのこれまでの本のテーマは、以下のようになっています。カッコ内は邦題です。
The Gifts of Imperfection (「ネガティブな感情」の魔法)- Be You. 自分自身であれ。
Daring Greatly(本当の勇気は「弱さ」を認めること)- Be all in. 全力でやろう。
Rising Strong (立て直す力)- Fall. Get up. Try Again. 倒れたら起き上がってまた挑戦しよう。
というメッセージでした。
それでは今回の4冊目の本は、どんな本なんでしょうか?
ひとことで言うと、Belongingに関する本です。
Belong、とは、何かに属すること。何かの一部になることですよね。クラブの会員になったり、会社の一員になったり。
著者のブレネーは、「何かの一部になっていると感じることは人間にとって不可欠なもの」であると過去の著書にも書いています。学校や部活で仲間にいれてもらえなかったりして辛い思いをした人も少なくないのではと思います。
何かに属しているという感覚は欠くことのできないもの、と信じていたブレネーは、マヤ・アンジェロウのインタビューを見て、ショックを受けます。
マヤ・アンジェロウは有名なアメリカの活動家、詩人、作家、女優ですが、1973年のTVインタビューでこんなことを言っていたそうです。
You are only free when you realize you belong no place – you belong every place – no place at all. The price is high. The reward is great.
自分がどこにも属さないと分かって初めて人は自由になるものです。—全ての場所に属して—どこにも属さない。その代償は高いわ。でも大きな報いがある。
これを初めて聞いた時、ブレネーは「それは違う」「どこにも属さない世界なんて」「彼女は属することのパワーを知らない」と思ったそう。そしてこのあと20年近く、この言葉が引用される度に怒りを覚えるようになったのだとか。
怒りの理由は二つ、一つは、ブレネーが尊敬するマヤ・アンジェロウが自分と正反対の意見を持っていることが許せなかったこと、そして、ブレネー自身にとって、「どこにも属さない」ことが辛い経験であったことです。
子供時代何度も引っ越しをしたため、ただでさえどこか一つの学校、クラブ、コミュニティに属することが難しかったというブレネーですが、高校生の時にベアカデッツ(話を簡単にするために、チアリーディングのようなものと考えて下さい)にどうしても入りたかった彼女の辛い体験談が書かれています。両親の仲が悪化している時で、キラキラした衣装に身を包んで、沢山の友達とダンスをすることが、一種の救いのように感じていたブレネーは、これまで何かをこんなに求めたことはないというくらいベアカデッツに入りたかった、と書いています。ベアカデッツの女の子達はなんでも一緒にやり、行動するのでベアカデッツは、まさに「所属感を擬人化したようなものだった」と。
ダンスは得意だったので、転校したばかりの学校で、一人で(まだ一緒に行くほど親しい友達が居なかったため)オーディションに参加したブレネーは、学校について唖然とします。
オーディションに参加した子達は全てメイクをばっちりして、派手な衣装に身を包んでいました。ブレネーと言えば、すっぴんで、黒いレオタードにグレーの短パンをはいていたそう。オーディションには思いっ切りドレスアップして挑むものだと、誰も教えてくれなかったのです。
それでも何とか気を取り直してオーディションを終え、夕方、結果発表のため、祖父母の家に行く途中で家族全員が乗った車で学校に行ったブレネー。
ドキドキしながら結果表を見ると、、、、彼女の番号は載っていませんでした。合格して喜びの声をあげる友人達をあとに、絶望して車に戻りました。両親は、彼女には全く一言もかけてくれなかったそうです。沈黙がナイフのように心に刺さったというブレネー。彼女の両親はどちらも若い頃は人気者で、父親はフットボールのキャプテン、母親もチアリーダーだったとか。両親は自分のことを恥じている、と感じたブレネーは、自分はどこにも属さない、そして、ついに、自分の家庭にも居場所がない、と感じたのだそうです。
今振り返って見ると、ブレネーはこれはもしかすると自分で創り出したストーリーだったかもしれない、と書いていますが、もしこのとき、彼女の両親が、オーディションに受からなかったことを慰めてくれて、挑戦しただけでも偉いと言ってくれたら、または(本当はこれが彼女が希望していたことですが)彼女を合格させなかったチームはひどい、あなたは合格する資質がある、と言ってくれていたら—この話は彼女ののちの人生の軌跡を定めるような話になってはいなかっただろう、と書いています。でも、実際にはそうなってしまった。
他人事なのに、読んでいて胸が痛くなる話です。
この話を本に書くことは思った以上に辛かったというブレネー。当時の練習曲をiTunesで聞いて思わず涙してしまったそうですが、それは、チームに入れなかった悔しさというよりも、当時、何が起こっていたのか分からなかった若い自分を慰めてくれる人が居なかったことへの涙だと言います。彼女の両親は当時は娘の痛み、そしてヴァルネラビリティに対応するためのツールもスキルも持ち合わせていませんでした。両親はその後離婚してしまいましたが、幸い、家族で勇気、ヴァルネラビリティ、そして真に何かに属するとはどういうことかを学ぶことができたので、この事件は彼女たちの未来に悪影響を及ぼすことはなかったと言います。
家族の中に居場所がないと感じることは最も危険な痛みで、これは3つの結果につながるとのこと:
1.ずっと傷つきつづけ、その心の痛みを麻痺させるか、または他人にその痛みを負わせてしまう
2.痛みを否定し、否定することで周りの人や子供達に引き継いでしまう
3.痛みを自分のものとして認める勇気を見つけ、自分や他人に対する思いやりを育て、世間で起こっている痛みをユニークな目でみつけることができる
2013年にブレネーはオプラ・ウィンフリーのSuper Soul Sundayという番組に出演することになります。そして同じスタジオに、長年尊敬してきたマヤ・アンジェロウが居る、会ってみたいか、とオプラに聞かれるのです。
この出会いのシーンはとても感動的なので、ネタバレしないでおきますので、本を読んでみるまでのお楽しみ。
そしてさらにそれから数ヶ月後、講演活動をしていく中で様々な出来事があり、やはり「自分はどこにも属していない、居場所がないのだ」とがっかりするブレネーは、ようやくアンジェロウの言葉の本当に意味に気が付くのです。
それでは真に属する(true belonging)とはどういうことでしょうか?
英語でfit inという表現がありますが、これは日本語でいう「迎合」に近いと思います。思春期にブレネーのような経験をした人は沢山いると思うのですが(私も含め)、どこか、何かに属したいがために自分を曲げたり取り繕ったりして迎合してしまう人も多いでしょう。でも、ブレネーは迎合することは属することの全く正反対だと言います。
自分に属する、ということは、誰がなんと言おうと自分の考えに忠実であること。それができてこそ、本当に自由になれるし、どこにも属さない。まるで一種の逆説のようで、最初読んだ時は私も「??」という感じでしたが、何度も読み返してみると、確かにその通りだと思いました。
自分の意見に忠実であれば、世間から非難されたり、後ろ指をさされることもあるかも知れません。ブレネーの夫のスティーブは小児科医で、抗生物質を処方しないことで親から非難を受けたりすることもあるそうですが、彼自身は「それはこの子供に必要ないものなので、誰に非難されても自分の意見を突き通す」というたとえ話をしています。
詩や文学、音楽の世界で、野生というものは広く恐ろしく危険な環境としてよく使われるメタファーです。ブレネーはこの野生/荒野/大自然というメタファーは、自分の考えに忠実であることと同じであると言います。それは孤独で、感情的で、スピリチュアルで、広大なものだからです。完全に自分に属しているということは荒野に一人で立ち向かうことと同じなのです。恐ろしく、危険な場所で、結果をコントロールできない環境ですが、この野生の場所こそが、もっとも勇敢で、神聖な場所と言えるでしょう。
真に属するとは自分を変えることではなく、自分自身でいること。
この本では、それでは勇敢に荒野に向かっていくために、何か必要なのかを一つづつ説明していきます。2016年の大統領選以来、波乱を極めるアメリカと世界の社会の中をいかにして進んでいくか。3章以降でその方法が詳しく説明されています。
私自身は、これまで彼女の本を読んできた経験から、自分自身をさらけだすこと(ヴァルネラブルである)こと、勇気を出して挑戦することには少しは慣れてきたと思っていましたが、この本では、自分1人に属するには、他人とも繋がらなければいけない、と説かれていて、これにはもう少し練習が必要なようです。
アメリカの大統領選以来、私達は自分と似た意見の人達とばかり固まるようになってしまいました。研究によると、そのように自分達を分けてしまうと寂しさが増えてしまう傾向にあるそうです。また、自分の味方でないならそれはすなわち敵である、というような偽の二極論を展開してしまいがちです。
ブレネーは、そのような二極論を止め、自分と意見の違う人の話をしっかり聞き、同意できない場合でも礼儀正しく接することの大切さを説いています。
この本の後半で、特に感動的なのが、私達は実は他人と密接に繋がっているのだ、そしてその繋がりを強めることによって、荒野に立ち向かうことができるのだと説かれている部分です。
私自身も、1人で公共の場にいる際、ついスマホだけをのぞいてしまい、タクシーの運転手さんと話をしなかったりすることがあります。昨今では、マンションのご近所同士でも殆ど話をしないことなどが普通になってしまっていますよね。
ブレネーは「人は近づくと嫌いになりにくいもの。もっと人に近づこう。」と言っています。どの政党を支持するかによって「共和党支持者はバカばっかり」などと言ってしまうこともありますが、1人1人をしっかり見ていくと、言うまでもないことですがみんなが悪人やバカな訳はありません。1人1人に近づき,その人を理解することが大切です。また、知らない人と手を繋ごう。という章では、スポーツや教会などでみんなが一体になることのパワーを説明し、ハリー・ポッターの映画を見て感動した人達が劇場で示したジェスチャーや、チャレンジャー爆発事故の際、ハイウェイで車を停めた人達など、集合体として、感動や哀しみを分かち合った時の様子がかかれています。
「自分に属すること」が荒野に立ち向かっていくことというのは、最初はなかなか理解しがたいコンセプトかも知れませんが、非常に大切なことだと思いました。
日本語訳はおそらく来年あたりに出版されるかと思いますが、それまで、この本について語ってみたいと言う方は、ぜひFacebookのグループへもどうぞ。
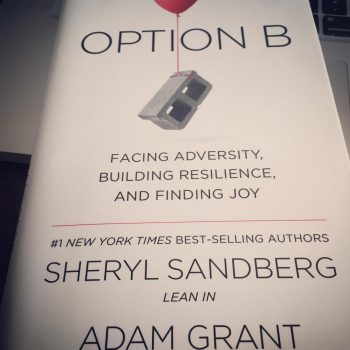
Facebook COOのシェリル・サンドバーグは女性がもっと積極的に仕事に進出することを薦めて書いた 『Lean In 』で有名ですが、2015年に夫のデイビッド・ゴールドバーグ氏を突然亡くしたことでも大きなニュースになりました。今日紹介する本『Option B』にはその夫の死後、彼女がいかにして強さを—いえ、それは「強さ」ではないかもしれませんが—いかにして最愛の伴侶の死という大きなトラウマから立ち直っていったかが書かれています。
タイトルの意味はシェリルのFacebookポストに書かれていました。デイビッドが亡くなったあと、父親が参加するイベントに、友人が代わりに参加してくれるよう予定を立てていたのですが、ふと” But I want Dave. I want Option A” と泣く彼女に“Option A is not available. So let’s just kick the shit out of option B.” と彼が言ったことからつけたタイトルだそう。
この本は彼女の親しい友人で心理学者のアダム・グラント(著書に”Give and Take”など)との共著です。私のお気に入りのポッドキャストにOn Beingという番組がありますが、この番組にシェリルとアダムがゲストで呼ばれたエピソードもここにシェアしますね。シェリルとアダムはアダムがデイビッドが当時CEOだった会社、サーベイモンキーで講演をして以来の友人だそうですが、デイビッドが亡くなった際、すぐに飛行機で駆けつけたのもアダムだったそう。
死や病気などの辛い出来事があった場合、 ”It’s going to be OK(きっと大丈夫)”といったあいまいな慰め方をしてくる人が多い中、「若い時に親を亡くした子供達でも立ち直って幸せな大人になっているという例は沢山ある」と、データや研究に基づいた意見をアダムから聞くことにどれだけ救われたか、シェリルはOn Beingでのインタビューでも語っていました。
シェリルは夫の死後30日を過ぎた時に投稿したFacebookポストにも触れています。シェリルは彼女の宗教であるユダヤ教では配偶者の裳に服す期間は30日なのに、30日経っても全く哀しみが癒えないことに絶望してこのFacebookポストを書き、「こんなの、絶対に投稿できない」と決めて最初はそのまま寝てしまったらしいのですが、翌日「これ以上状況が悪くなるわけもない」と思い直して投稿し、多くの人々の共感を呼び、これは4千万回以上もシェアされました。
誰かが大切な人を亡くしたとき、癌などの深刻な病気になったとき。人は間違ったことを言ってしまうのではないかということを恐れて、結局なにも言わないことが多いと思います。シェリルも、夫が亡くなった後、誰もデイブのことを口にしなくなったことを”Elephant in the room(見て見ぬふりをされている問題”)と言っています。かといって、 “How are you?” と普通に聞かれても、「私の夫は死んでしまったのよ。元気なわけないじゃない!」と叫びたくなったというシェリル。でも、皆が間違ったことを言うことや、傷つけることを恐れて大切なことを口にしなくなった時、問題の当事者はさらに傷つくのだとシェリルは言います。病気で息子を亡くした作家のMitch Carmody は“Our child dies a second time when no one speaks their name— 人が私達の子供の名前を口にしなくなった時、彼等はもう一度死ぬことになる” (P33) と言っています。愛する人を亡くした人達は、彼等のことをいつまでも覚えていたいのですよね。
そして実際にトラウマを経験した人には代わりのあいさつとしてHow are you today? と聞くのはどうだろうか、そして今では、辛いことが起こった人には、何も言わないのではなく、”I know you are suffering, I am here.”と言うようになったと話していて、実際の生活でとても役に立つエピソードだと思いました。
また心理学者のマーティン・セリグマンによると、愛する人の死やレイプなど、大きなトラウマを経験した際、3つのPが立ち直りを防いでしまうのだそうです。その3つのPとは:
(1) Personalization—トラウマの元となった出来事は自分のせいだという考え
(2) Pervasiveness—その出来事が自分の人生の全ての面に影響するという考え
(3) Permanence—出来事の影響は永遠に続くという考え
だそうで、これをいかにして取り除くかがカギとなっているそうで、これもとても役に立つ情報でした。
アダムは心理学者なので、シェリルが「最愛の人が亡くなってしまって、もうこれから一生幸せなんて感じることはない」と打ち明けた際も、アダムは「それはPermanence という罠だよ。それにデイビッドが死んだのは自分のせいだと思うのもPesronarization という罠。罠を避けて、君が回復しないと、君の子供達も絶対に回復しない」と言われ、子供達が立ち直るためなら何だってする、と積極的に立ち直りへの道を歩むようになったのだとか。またこのような研究に基づく証拠を示してくれたことでとても心強かった、と話しています。
また、トラウマから立ち直る際役に立ったことが、意外にも「最悪の状況を想定する」ことだそうで、シェリルは「愛する夫を亡くして、これ以上ひどいことなんてあり得ない」と思っていたものの、アダムに「それよりひどいことはあり得る。例えばデイブが発作を起こした時、二人の子供を乗せて車を運転していたらどうなっていた?」と聞かれ、瞬時に「私にはまだ子供達がいる。私はなんてラッキーなんだ」というGratitude(感謝の気持ち)が湧いてきたといいます。最悪の状況を想定することは、一見逆効果のように見えますが、実はこれが、立ち直りに必要な感謝の気持ちを産むものなんですね。
それにしても、この本のテーマが「いかにしてトラウマから立ち直るか」なので当たり前といえば当たり前なのですが、この本には辛い経験をした人達が沢山でてきます。レイプの犠牲者、息子を亡くした親、二人の子供を乳母に殺された親。。。それぞれの状況を読む度に胸が痛みますが、みな、辛い経験を糧にして立ち直った人ばかりで、希望をもらえます。
トラウマを経験した人にどう接するか、の他にも、トラウマを経験したあとそこから学んで成長することは可能なのか?というトピックにも触れられています。英語ではPost-Traumatic Growthとなっていますが、このセクションでも、多くの辛い経験を経てさらに成長した人達の話に、きっとインスパイアされるでことでしょう。
とても感動的だったのが、家族でいつも遊んでいたボードゲームを思い切って子供達とプレイすることにした話や、デイブが好きだったGame of ThronesのTV番組を見るようになった、というくだり。デイブが好きだったものをいつまでも避けているのではなくWe take it backと宣言して、彼が好きだったものをもう一度楽しむ姿に感動しました。そして、喜びを感じることに罪悪感をもたないこと。サバイバーズ・ギルトというのはよく知られている心理学用語ですが、デイブの死後、嬉しいこと、楽しいことを感じる許可を自分に与え、喜びを感じることに罪悪感を持たないこと、そして、その日あった嬉しいことや感謝することを寝る前にメモするようになったとも書かれていました。
最後に、おそらくこの本の中で私が個人的にもっともインスパイアされた部分は、老いていくことは生きている私達だけにもたらされた特権であるということ。
シェリルは今まで、誕生日が来る度に、年取るのは嫌だな、とか、誕生日なんてたいしたことじゃない、と特に何もせずに過ごしてきたらしいのですが、デイブが50歳を目前にして亡くなった今、年を取るということがなんと恵まれたことなのか実感したとシェリルは言います。We either grow old or we don’t. 私も、1日でも長く生きれることに感謝したいと思いました。
この本に出てくる多くの人がトラウマから立ち直る姿に、きっと勇気をもらえるはずです。
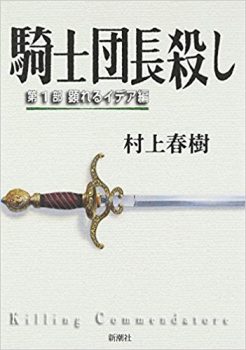
13歳の時に「ノルウェイの森」を読んで以来ずっと村上春樹の本を読み続けています。いわゆる「ハルキスト」ではありませんが、日本の作家で毎回新作が出るたびに読み続けるのは彼だけです。
いつもは新作がでるとすぐにアマゾンで購入してカナダまで取り寄せるのですが、今回に限りタイミングを逃し、そのうち読まねば、と思っていたらすでに3ヶ月以上経っていました。幸いビクトリア在住のお友達が親切にも貸してくれたので、一気に読みました。
「騎士団長殺し」
読む前はタイトルの意味もよくわからなかったのですが、読んでみるとこのタイトルも各部につけられたサブタイトル「顕れるイデア編」「遷ろうメタファー編」も、読んでみるとまさにそのままなんだけど、渋すぎる。良い!
(以下ネタバレありますのでご注意)
SNSやGoodreadsのレビューにも書きましたが、これは典型的な春樹ワールドでした。主人公は肖像画を描くことを生業にする画家で、離婚のため、友人の父親である、とある有名画家の家に一時的に身を寄せるところから話は始まります。妻に去られ、一人で静かに暮らす様子は世界観としては「ねじまき鳥クロニクル」、また後半の冒険部分では私が大好きな「ダンス・ダンス・ダンス」や「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」(この二つは私の中で村上作品のトップ2です)を彷彿とさせます。
春樹ワールドにおなじみの「美少女」「井戸」「恐ろしくチャーミングで裕福な男」「物が無くなる・人が消える」「壁抜け」「孤独」「音楽」「料理」「歴史」などがふんだんに盛り込まれていて読み進めながら「キタ−!」とワクワクしながら一気に読んでしまいました。
アンチ春樹の人はこういうところが嫌いなんでしょうけど、、、私は逆にそれが彼のスタイルだと思っているので、逆にないと面白くない。登場人物の会話も、「誰も『あるいは』とか普段の会話で使わないっしょ」と、ツッコミながら読むのが逆に面白いという。
ストーリーの流れとしては、キャラクターや設定が変わっているだけで、著者が意図したことなのかどうかはわかりませんが結局は過去作品と同じような気がしました。平和な生活→妻に去られる→一人→不思議なものを発見して話が展開。。。という。
有名画家の家に移り住んだある日、主人公は屋根裏部屋をみつけ、そこに隠されていた「騎士団長殺し」という絵を発見して、そこからどんどんと不思議な話が始まっていきます。
今までと全く違う村上作品を期待していた人や、過去2作「女のいない男達」や「色彩を持たない多崎つくる」のような本を期待していた人はがっかりするかもしれませんが、私は、「これっていつものパターンだよね」と思いつつも、そこまで気になりませんでした。思うんですが、世間の人って結局同じものの繰り返しが好きなんじゃないかなと思うんですよね。だって、Wes Andersonの映画とか、つまりは決まったスタイルを保った同じような映画ですし。
ただパターンが過去の作品に似てくるとつい先を予測してしまうというのは困りました。「この人絶対怪しい」とか「この人死にそうだな。。。」とか色々考えてしまいましたね。それも読書の楽しみのひとつなのかもしれませんが。
もちろん不思議なことも沢山起こります。起こるに決まってます。この「不思議系」で村上作品の好き嫌いは分かれるようですが。。。
後半のクライマックスのシーンでは、「ハードボイルド・ワンダーランド」の「やみくろ」を思い出しました。(しかしあの作品は今でも傑作だと思う)
最後のオチが個人的にはうーん、もう一踏ん張り欲しかった、という感じでしたが、これってもしかして「ねじまき鳥」みたいに後で3部が出たりするんでしょうかね?第2部の最後は(第2部終わり)としか書かれてないし。回収されない伏線や説明されなかった部分がいくつかあって、そのあたりが気になりましたが、全体としては楽しめたのでよしとします。読んだ方、ぜひコメントで感想シェアして下さい。
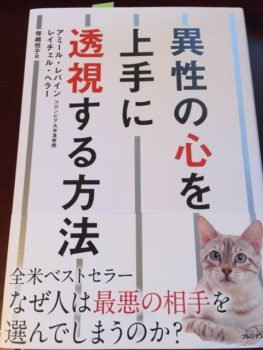
国際結婚コンサルタントの塚越悦子さんとは、WDS(世界征服サミット)で知り会い、以来仲良くさせていただいている「同士」です。最近は一緒にブレネー・ブラウンのLiving Brave Semesterのコースを一緒に取ったりしています。その悦子さんから「異性の心を上手に透視する方法(プレジデント社)」を送って頂きました。悦子さんは「国際結婚一年生」という本を出版されていますが、今回は初めての翻訳本とのことで、興味深く読ませていただきました。
私自身は再婚して今年で4年目ということもあり、婚活をしている訳でもないので「異性の心を透視」する事がそこまで重要とは思えなかったのですが(苦笑)、これが読んでみると非常に興味深く、「ひえー」と思いながら読んでしまいました。
タイトルだけ見るとパートナーや恋人を探している人のみに向けた本のように思われる方もいるかもしれませんが、すでにパートナーが居る人でも十分に参考になる情報が沢山詰まっていました。
原題は”Attached”というこの本はアミール・レバインとレイチェル・ヘラ−両氏による共著ですが、心理学の愛着(アタッチメント)理論を元にした科学的な恋愛ストラテジーの本です。
本の最初で紹介されるのがアタッチメント・タイプ(愛情タイプ)です。すべての人は3つの愛情タイプのどれかにあてはまるそうです。その3つのタイプとは:
Sタイプ(Secure:安定型):相手と親密になることは自然なことだと思っている人。
Nタイプ(Anxious:不安型): パートナーとの親密さは無くてはならないもので、時には相手に夢中になりすぎたり、相手が愛してくれないのではと不安になる人。
Vタイプ(Avoidant:回避型): 親密さは自由の喪失を意味するので、交際している相手がいても、常に距離を置こうとする人。
となっています。自分が一体どのタイプにあてはまるのかは本文中のテストで見極めることができますが、私が一番ショックだったのは、自分がVタイプだと発見したことでした。ガーン。
でも確かに言われてみるとあてはまることばかり。さすがに「飽きた」という理由でつきあっていた人と別れたことはありませんが、愛情表現を沢山されると鬱陶しいと思ってしまうんですね。これは、相手と親密になりすぎないようにする「離別ストラテジー」というものなのだそうです。さすがに結婚している今は、オットを突き放して別れようとしたり(汗)はしませんが、つい素っ気なくしてしまうのですね。Vタイプの人は自由を求め、自立がもっとも大切なことと信じる人が多いそうで、本当の「自立」の意味を勘違いしている人も多いとのこと。Vタイプについて説明した章の始めに、私がとても影響をうけた映画「荒野へ(Into the wild)」のことが書かれてます。主人公クリスは自立に憧れ、アラスカの自然に一人で向かい、最終的には亡くなってしまうのですが、彼が日記に残した「Happiness only real when shared.(幸福は誰かと分かち合ってこそ本物になる)」という一言に、深く頷いてしまいました。Vタイプの人は他人から寄せられるサインを読むのが苦手というのも、耳が痛い(苦笑)指摘でした。でも、本文中にでてくるジョン・グレイ博士(「ベスト・パートナーになるために:男は火星から、女は金星からやってきた」)ももとはVタイプだったそうですが、奥さんとのトラブルの上Vタイプの弱点を知り、その後Sタイプに近づく努力をしているそうです。なのでNタイプやVタイプの人でも、努力してSタイプに変わることだって可能なのです。
ちなみに、うちのオットはSタイプです。愛情表現を出し惜しみしないタイプですね。だからかろうじて(汗)上手くいっているのかも。
この本にはNタイプ、Vタイプの人へのアドバイスの他、Sタイプに近づくにはどうすればいいか、そして「最悪の組み合わせ」からいかにして抜け出すか、そして本の後半は「相手に気持ちが伝わる5つの習慣」や「けんかを乗り切るための5つの習慣」など、パートナーとの幸せな関係を長続きさせるコツが色々と載っていますのでぜひ参考にして下さい。
*悦子さんからこの本を一冊頂いていますので、興味のある方は9月4日までにコメントでお知らせ下さい。複数の方からコメントがあった場合には抽選で選ばせて頂きます。(北米在住の方に限らせて頂きます。ご了承下さい。)

私は林真理子氏のエッセイが大好きで、 「ananを後ろから読む女」とはまさに私のこと。彼女のエッセイ集「美女入門」シリーズはほぼ全巻持っているし、週刊文春のほうのエッセイ「夜更けのなわとび」他、単行本になると必ず買っています。
小説のほうは、エッセイほどマメに読んでいるわけではなくて、時々見つけては読み、という程度です。今回はビクトリアの図書館で「下流の宴」を見つけたので読んでみました。
「下流社会」なんて本も昔ありましたが(読んでません)この「下流の宴」はなんとかして「上流」に行こうともがく人々を描いています。主人公の由美子は医者の娘で、国立大を卒業したもののメーカー勤務の夫と結婚した2児の母で、プライドが高い。「下流」の人達を「あっちの人達」などと呼んで、自分とは別のクラスの人間だと信じている。長女の可奈は見栄っ張りで、名門女子大に入ってからはなんとかして金持ちの男と結婚しようと目を光らせている。
次男の翔は母や姉とは違って野心もなく、高校を中退して漫画喫茶でアルバイトをすることになり、母の由美子をやきもきさせます。
ストーリーは由美子、可奈、翔の「福原家」と、翔がゲームを通じて知り合い同棲するようになった沖縄出身の珠緒の「宮城家」の話が章ごとに交代に語られるのですが、「下流」に対する偏見がひどくて(もちろん著者は意図しての事だと思うが)あまり良い気分になる本では無かったかな。。。
特に沖縄出身で両親が離婚して母親が飲み屋をやっているということでの由美子の偏見がひどい。自分の息子を絶対に「あんな女」とは結婚させないと息巻く由美子の様子がこっけいでもあり不気味でもあり。
「ここまで世間体や体裁を気にする見栄っ張りな人、いるの?」と思わず疑ってしまいましたが、やっぱり、居るんだと思います。幸い、私の周りにはいませんが。
格差社会の実情を描いて風刺しているのだろうけど、今ひとつピンと来なかったというのが本音です。

読んだ本1000冊紹介するシリーズ、5冊目にして日本語の本を初めて紹介します。
実はこの本の著者の平野啓一郎氏、私は全く知らなくて、毎日新聞での連載小説「マチネの終わりに」をnoteでも掲載していたのを読んで初めて知りました。海外に住んでいると誰の本が売れているか、等ということにとんと疎くなってきますね。
自分の好きな作家の本、又は電子書籍がでている作品ばかり読むようになってしまう上、週刊誌やテレビからの情報というのがまず入ってこないので、好みがだいぶ偏ってきます。
私はSFなどよりも、人の何気ない日常の美しさ、儚さなどを描いた作品が好きで、そういう意味では「マチネの終わりに」はとても好きな作品でした。話がそれますが、先日リース・ウィザースプーン主演で映画化されたシェリル・ストレイドの「Wild」(邦題は「わたしに会うまでの1600キロ」)という作品も、母が亡くなったことで心に傷を負って一人でバックパックを背負ってひたすらアメリカの国立公園を歩く女性の心の旅を描いたものでしたが、私はとても感動して素晴らしい作品と思ったのに、友人は「Nothing Happens!」と憤っていました。こういうのは好みの問題なのでどうしようもないですが。「マチネの終わりに」はいわゆる「ボタンの掛け違い」のような、ほんの一瞬で行き違ってしまった男女の運命のお話で、とても美しく描かれていたと思いました。
なので、ちょうど「マチネ〜」を読み終わったあと、とある友人が「空白を満たしなさい」を薦めていたのをみて、すぐに電子版を購入して読み始めました。
一度死んだのに何故か生き返った「復生者」、徹生の物語。
電子版では上・下に別れていますが、上巻は物語のペースが早く、ちょっとミステリーっぽいので、先が気になりあっという間に読み終えてしまいました。ネタバレはしませんが、下巻では徹生が生き返って、周りの生活に馴染んでいく様子、そして他の「復生者」と知り合ったり、人間の他者との関係を深く考えたりする様子が描かれています。著者の平野氏は「私とは何か」というノンフィクションを出されていることもあり、「分人」のコンセプトについても「空白を満たしなさい」の中でも詳しく説明されています。
結論からいうと、上巻で煽られた期待が下巻で実を結ばずがっかり。「これはこういうストーリーだろう」と勝手に思っていたものが、読み進めるうちに「あれ?」となり、「もうページ数ないよ?どうやって結論つける?」という焦りに変わり、最後は「。。。」となってしまいました。もちろん、薦めてくれた友人は絶賛していたので、この作品が好きな人は沢山いると思うのですが、私には予想と違った結末で、ちょっと残念でした。もちろんこれは私がミステリーという勝手な憶測で読み進めたからであって、「空白〜」はつまらない作品という訳ではないと思います。個人的に、私も「死」について考えることは良くあるので、じっくり考えてみたい人にはお勧めです。そして、タイトルが秀逸で素敵。
当たり前の事ですが、自分が好きな作家の作品の中でも気に入った作品とそうでない作品があるのですから、これに懲りずに、平野氏の他の作品も読んでみたいと思いました。
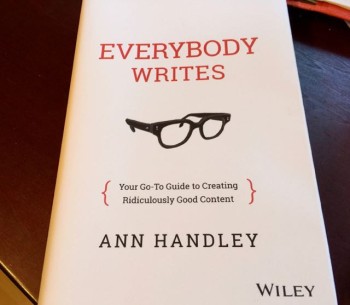
今日ご紹介する本はEverybody Writes (邦訳版タイトルは「コンテンツ・マーケティング64の法則」)です。邦題を見ると、コンテンツ・マーケティングの本か、と思う人が多いかと思いますが、原題はEverybody Writes。小説家やジャーナリストでなくても、ブログ、ソーシャルメディアの投稿、企画書など、今はみんながものを書く時代ですよね。これは読み手に意図がしっかり伝わるものの書き方を伝授してくれる本です。
著者のアン・ハンドリーはMarketingProfsというコンテンツマーケティングの会社のCCO(コンテンツ最高責任者)で、私もソーシャルメディア上でのお友達ですが、とっても良い人です。ソーシャルメディア上の影響力リストでは常にトップに名前が載る人ですが、偉ぶったところがなく、コンテンツマーケティングでは右にでるものがいない、いわゆる業界のリーダー的存在です。
この本は英語版ではものを書く際のヒントが74項目入っているのですが、なぜか日本語版では64になっています。私の勝手な推測ですが、いくつかの章は英語でしか通用しないルールだったりしたからかな?
私の手元には英語版しかなく、ちょっと日本語版を見てみましたが、章ががかなりちがって分けられており、どの章といっても日本語版を読む方には全く意味ないものになってしまうので、「法則」だけに注目して書くと、「ライティングはアートではなく習慣である」「最も重要なことを最初に書く」「読者の身になって書く」など、初心者むけアドバイスから「どのような単語を避けるべきか」「文法の基礎」「意味を間違って使っている可能性がある単語」「説教くさくなるな」まで、必要に応じて拾い読みできるようになっています。
ハンドリーは前作の「Content Rules /お客が集まるオンライン・コンテンツの作り方(C.C. Chapmanとの共著)」にて良いコンテンツを作る際、ストーリーテリングがいかに大切かを説いていますので、このへんがおさらいで含められているのも便利。またオンラインで物を書く際の基本(出典をきちんと表示する、著作権の問題)からブログなどのマーケティング素材はどのくらいの長さが適当か、Twitter、Facebook、Linkedin、Eメール、サイトのランディングページなどそれぞれのメディアへの書き方とヒントが詳しく書かれています。最後の方では、物を書く際に使える様々なツールのリストが載っており、これだけでもかなり便利です。巻末に索引があるので「あれなんだったけ?」という時に後で調べることもできるようになっています。
英語で物を書く機会がある方は是非英語版を読まれることをオススメします。
前回のブログ「人生でやるべきことが見つからない人へ」でも紹介した「食べて、祈って、恋をして」の著者、エリザベス・ギルバートの最新作「Big Magic: Creative Living Beyond Fear
」を読み終えました。
彼女のかつての最初のTEDトークは、「創造性をはぐくむには」というタイトルで、私もこれはとても好きなトークのひとつですが、このBig Magicもその創造性ーCreativityに関する本です。
ギルバートは今までにも小説を書いたり、「食べて、祈って、恋をして」のような自分の経験に関するノンフィクションを書いたと思ったら、前作は「The Signature of All Things」というタイトルの、植物学者に関する小説だったりで、なかなかバラエティに富んだ作品を送り出している人ですが、今回のBig Magicも、自分の経験に基づいた話が沢山紹介されているノンフィクションです。
私自身、2015年の言葉の一つを「Create」と決めて、今年は様々な創作活動に力を入れることにしていたので、なかなかタイムリーなトピックです。
一体どんな内容なのかと思って読んでみると、各章の中がとても短い(時には1ページのみ)トピックでまとめられており読みやすく、真っ先に頭に浮かんだ感想は「これって、スティーブン・プレスフィールドじゃん」ということ。
プレスフィールドもいわゆる自己啓発系(これは日本では必ずしもポジティブな言葉ではないかもしれませんが)の作家の中では非常に有名な作家で、「自己啓発系」だからといっておざなりにするにはもったいない作家です。有名な著書に「The War of Art」(邦訳版は「やりとげる力
」)「The Authentic Swing
」などがあり、これらは私も個人的に超お勧めですが、それはさておき。
創造性(クリエイティビティ)とはいったい何でしょうか?
巻頭に、こんな質問が載っています。
Q. What is creativity?
A. The relationship between a human being and the mysteries of inspiration.
ギルバートは、人は全て心の奥深くに埋められた宝石のような創造性をもっており、それを掘り出して何かを創り出すことが必要であると説いています。
最初の章で、リズ・ギルバートは、ニアミスだったものの結局は会うことのなかった同じ名字のジャック・ギルバートという作家について触れています。大学で教える傍らひっそりと自分の小説を書いていたジャック・ギルバートは、生徒達にクリエイティブな人生の勧めを常に説いていたそうです。
ジャック・ギルバートはとある詩のクラスのあとで一人の生徒を呼び出しました。とてもよく書けている、と彼女の作品を褒めたあと、彼女は将来何をしたいのか聞いたそうです。生徒は、ためらいながらも作家になりたいと伝えました。するとギルバートは「そのための勇気はあるかい?作品を前に出していく勇気が。君の中には宝物が隠されていて、君がきっと”Yes”と言ってくれるのを待っているのさ」と伝えたそうです。
ここでいう「創造」とは、必ずしも絵画や彫刻のような「美術」的なものとは限らず、音楽、クラフト、執筆、イラスト、アクセサリー創り、ガーデニング、写真、演劇、料理、スポーツなどなんでも良いのです。
でも、多くの人が、たくさんのことを怖がっています。あえてクリエイティブな人生を送らないのは、怖いから。
何が怖いかというと:
—自分は才能が無いのではという恐れ
—せっかく作品を世に出してもそれが受け入れられなかったり、反発されたり、嫌われたり、無視されるのではという’恐れ
—自分の創造性が活躍できる場所がないという恐れ
—他人の方が自分よりうまくできるという恐れ
—すでに他人は似たようなことをやっているという恐れ
—誰もまじめに受け取ってくれないという恐れ
—成功しないのではという恐れ
—恥ずかしいという恐れ
—きちんとしたトレーニングや教育を受けていないという恐れ
—誰かのマネをしているだけだと言われる恐れ
—周りの人になんと言われるかという恐れ
—すでにピークを過ぎてしまったのではという恐れ
—すでに年を取り過ぎているという恐れ
—まだ若すぎるという恐れ
—一度大成功したので今度はうまくいくはずがないという恐れ
—今まで一度も成功していないので何故いまさら挑戦する必要があるのかという恐れ
etc etc…
もう、怖いことばっかりですね。
著者のギルバートも、以前は怖がってばかりの少女だったといいます。でも、そのうち、恐怖というものはつまらないものだと気がついたといいます。何かを恐れて何も行動を起こさずにいると、もちろん何も起こらないので、ひどく退屈だというのです。また、あなたが感じている恐怖は他のみんなも感じている恐怖であり、まったくオリジナリティがありません。自分のなかに、ひっそりと、またふつふつとわき上がる「これやってみたい」「面白そう」という好奇心は、人それぞれ違っており、オリジナリティのかたまりのようなものです。
二章目のEnchantmentでは、クリエイティビティ、そしてインスピレーションがどのような動きをするのかについて書かれています。TEDトークでも紹介されている詩人のRuth Stoneの話が再度この本でも紹介されており、インスピレーションは突然降ってくるもので、「それ」がやってきたら急いでペンをつかみ、なんとしてでもそのしっぽを捕まえなければいけない、というのは私も特に好きなエピソードです。
そしてタイトルの通り、ときにインスピレーションと創造性は、まさに魔法のような働きをします。ここに書いてしまうとネタバレなので書きませんが、ちょっと信じられないような逸話が紹介されています。
第三章は「許可」について書かれており、クリエイティブな人生を送るのに、誰の許可もいらないんだよ、ということが説かれています。また、クリエイティブなことをするのに「世界を救うため」「人を助けるため」などという大それた理由も必要ないと言います。ただ、自分がやりたいから、絵を描く。本を書く。スケートを習う。料理する。家のペンキを塗る。手紙を書く。歌のレッスンを取る。写真を撮る。それで良いんです。
第四章はPersistence、粘り強く続けることについて書かれています。この章は主に著者の作家としてのキャリアについて書かれており、なかなか興味深い逸話が載っています。
第五章は「信頼」、Trustについて書かれています。前回のブログでご紹介した「情熱vs好奇心」の話はここに書かれています。著者の前作の植物学者を題材にしたThe Signature of All Things、という本も、今までとはちょっとジャンルが違って面白いなあと思っていたのですが、この本を書くことになった経緯も、好奇心がもとだったそうです。
また、失敗から立ち直る方法として、とにかく、なんでも良いからやってみる、失敗にこだわりすぎず、気分転換に何か他のことをやる、などが紹介されています。私もこの数週間ちょっとスランプ気味ですが、開き直って、編み物などやっています。すると、自分の中の別のチャンネルが開いてくるような気がするのが不思議です。
内容的には、そこまでま新しいことが書かれているわけではありませんが、著者独特の軽くユーモアに満ちた語り口で、スイスイ読めます。
最近右脳を使うクリエイティブなことをやっていないなという方、人生をもっとクリエイティブに生きてみたい方は是非いちど読んでみて下さい。